
芥川龍之介の名作として有名な『羅生門』ですが、初めてこの作品に触れたのが学校の教科書という方も少なくないのではないでしょうか。
その時にこの作品を面白いと思うかどうかは人それぞれだと思いますが、ここではそんな小説『羅生門』のあらすじと解説をしていきたいと思います。
{tocify} $title={目次}
芥川龍之介について
『羅生門』についてお話しする前に、まずは作者である芥川龍之介について簡単に説明します。
実は、芥川龍之介という作家はあまり長編小説を書きません。
長編小説の定義がよく分かりませんが、青空文庫に存在する芥川龍之介の作品で最も長い小説で5万字ほどです。
5万字って長いじゃんと思われるかもしれませんが、夏目漱石の『こころ』が17万文字、『吾輩は猫である』が34万字と言えばどうでしょうか。
ちなみに夏目漱石の『こころ』について解説した記事もありますので、
夏目漱石の『こころ』(上中下)のあらすじを簡単に解説!
高校の現代国語で習う夏目漱石の『こころ』ですが、全文を読んだことがある人は案外少ないのでは?本文の引用も含んだ『こころ』上中下のあらすじを徹底解説。私と先生の出会い、そして先生とKとの関係、Kの自殺までを丁寧に読み解いていきます!
よろしければこちらをご覧ください。
何度も言いますが、この5万字という芥川龍之介の作品は彼の全ての作品の中で最大文字数です。
この『羅生門』に至っては6267文字という短さです。
しかし、そんなに短い文章であるにも関わらず、多くの人を魅了する名作を作り出せてしまうのが芥川龍之介の天才的センスなのです。
芥川龍之介が描く小説一本の文字量は少ないかもしれませんが、作品数の量に関してはとてつもないほど多くの作品を残しています。
夏目漱石の作品数が110作品に対して芥川龍之介は372作品と三倍以上の作品数を残しています。
もちろん芥川龍之介よりも多くの作品を残している人は山ほどいます。
しかし、彼は自殺により短命でもありました。
芥川龍之介の人生は35年です。
自殺したことで有名なもう一人の代表的な作家である太宰治ですら38歳の生涯でした。太宰治よりも芥川龍之介は短い人生だったのです。
前置きが長くなりましたが、そんな若くして文才の塊だった芥川龍之介の名作『羅生門』とは一体どのようなストーリーなのでしょうか。
登場人物から見ていきましょう。
『羅生門』の登場人物
『羅生門』の登場人物は極めてシンプルです。
男と老婆と死体。
以上です。
登場人物は全員、名前すら分かりません。
まずは主人公である男から見ていきましょう。
男
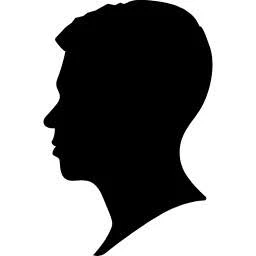
洗いざらした紺の襖(あお)の尻を据えて、右の頬に出来た、大きな面皰(にきび)を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めていた。
男は下人(げにん)と書かれています。
下人とは
① 身分の低い者。②下男。しもべ
という意味だそうです。(by広辞苑)
しかし、この下人は現在リストラにあり、無職男になってしまっています。
それが分かる部分がこちらです。
主人からは、四五日前に暇を出された。
「暇を出す」は使用人などをクビにするという意味です。
まぁ、休暇を与えるという意味もあるようですが、この『羅生門』では男は完全にクビにされてしまっています。
そして時代設定ですが冒頭に
羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみをする市女笠(いちめがさ)や揉烏帽子(もみえぼし)が、もう二三人はありそうなものである。
とあり、市女笠、揉烏帽子というワードや羅生門が平安時代に実際にあった羅城門をモデルにしていることなどから時代設定としては平安時代と伺えます。
なので、この小説『羅生門』の主人公は平安時代の元使用人であるしがない男と推察できます。
老婆

檜皮色(ひわだいろ)の着物を着た、背の低い、痩やせた、白髪頭(しらがあたま)の、猿のような老婆である。
老婆は羅生門の梯子を上った楼で男が出会った人物です。
主人公である男の顔の描写はそんなにありませんが、この老婆に関しては多くの描写がされています。
丁度、鶏(にわとり)の脚のような、骨と皮ばかりの腕である。
眶(まぶた)の赤くなった、肉食鳥のような、鋭い眼で見たのである。それから、皺で、ほとんど、鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で、尖った喉仏(のどぼとけ)の動いているのが見える。
老婆の見た目に関する描写がされているところを見るに、よっぽど芥川龍之介はこの老婆のみすぼらしさを強調したかったのではないかと思います。
老婆は羅生門の二階部分で死体に囲まれ、頭髪の窃盗をしていたところを、主人公ある男に見つかってしまうのです。
死体(女)

その老婆は、右の手に火をともした松の木片(きぎれ)を持って、その死骸の一つの顔を覗きこむように眺めていた。髪の毛の長い所を見ると、多分女の死骸であろう。
この女性の死体は羅生門の楼に捨てられていたところ、老婆によって髪の毛を抜かれてしまいます。
その衝撃的シーンがこちら。
すると老婆は、(中略)今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、丁度、猿の親が猿の子の虱(しらみ)をとるように、その長い髪の毛を一本ずつ抜きはじめた。髪は手に従って抜けるらしい。
老婆が女性の死体から髪の毛を抜いているシーンを男が見たことにより、男が老婆に対して悪に対する反感を持つようになるところがこの『羅生門』の一番のキーポイントです。
ちなみにこの女性死体ですが、生前は詐欺を行っていました。
蛇を魚と偽って人にそれを売っていたようです。
『羅生門』あらすじ
それでは芥川龍之介が描いた小説『羅生門』を超絶ざっくりのあらすじでご紹介したいと思います。
男、羅生門にやってくる
あるところに一人の男がいました。

あぁ…、仕事クビにされたし、これからどうしたらいいんだ…
男は途方にくれて羅生門の下でたたずんでいました。

無一文だし、ここは盗人になるしか…。いや、ダメだ!俺にそんな勇気はねぇ!とにかく、今日泊れる場所を見つけないと…
すると男は羅生門の上に上る梯子を見つけました。

そうか、門の上にならば屋根がある。最近は羅生門の上に死体を捨てていく人が多いって聞いたことがあるけど、屋根があるだけましだ。よしっ、門の上で一夜を過ごそう
そう考えた男は羅生門の梯子を上っていくのです。
男、老婆を発見する
梯子を上っていた男は不思議なことに気が付きました。

なんだ。光が漏れている。上に誰かいるのか?こんな死体だらけの場所にいるやつなんて、ただ者じゃないはずだ…
男は恐る恐る羅生門の梯子の先である二階部分を覗き込みました。
すると、そこには痩せた一人の老婆がいたのです。

何をしているんだろう?
薄気味悪いと思いながらも男は老婆を観察しました。
すると老婆は数ある死体の中から女性の死体を選んで、髪の毛を一本ずつ抜き始めたのです。
その様子を見た男はとてつもない憤りを感じました。

何をしているんだ、この婆さん!死んだ人の髪の毛を抜いて一体どうするつもりだ!
そして男は持っていた刀に手をかけながら、老婆の前に姿を現したのです。
老婆、説明する
急に目の前に現れた男に老婆は驚き、慌てて逃げようとします。

待てー!逃がすか!
男と老婆はしばらくの間つかみ合いになりました。
しかし、男の力の方が老婆より強いのかは明らかです。
男は老婆に刀を向けました。

何をしていたのかを言え。言わねば、斬るぞ!
刀を向けられた老婆は怯えでがたがたと震えることしか出来ませんでした。
何も言わないでただ怯えている老婆を見ると男の中で老婆への征服感が高まり、いくぶん男の声色も柔らかくなりました。

俺は警察でもなんでもない。ただの通りかかりだ。だからお前を逮捕とかはできない。しかし、お前がここで何をしていたのかが気になっただけだ。お前は本当のことを話してくれたらそれだけでいいんだよ
男の言葉を聞いて老婆はやっと口を開きました。

死人から髪を抜いて、かつらを作ろうと思っていたんじゃ
男は老婆の理由を聞いて、なんだそんなことかと若干失望し、また同時に老婆に対して冷ややかな侮辱も感じました。
そんな男の気持ちが老婆に伝わったのか、老婆はこう続けます。

確かに死人の髪の毛を抜くという事は悪いことかもしれん。しかし、わしが今髪の毛を抜いたこの女だって、生きていた時には詐欺をしておった。わしは、この女がしたことが悪いとは思っておらん。そうしなければ餓死をするので、仕方なくした事なのであろう。ならば、わしが今していることだって悪いことではないはずじゃ。わしだってこれをせねば餓死してしまうので、仕方なくしていることなのじゃからな
男は黙って老婆の話を聞いていました。
男、心が固まる

なるほど、そういうことか
老婆の話を聞いた男は一人納得し、老婆の襟をつかみました。

では、俺が今から婆さんの着物を奪ったって恨むなよ。俺もそうしないと餓死してしまう身の上なんでな
そう言うと、男は素早く老婆の着物をはぎ取りました。

なにするんじゃー!
老婆は男の足にしがみつきましたが、男はそれを蹴飛ばしました。
そして男は急いで羅生門の梯子を下っていったのです。

…一体、何があったんじゃ
男に蹴られて、しばらく死んだように倒れていた老婆でしたが、なんとか這いつくばって梯子の下を覗き込みました。

いない…か
そこにはただ黒々とした闇がひろがるばかりでした。
男の行方は、誰にも分かりません。
『羅生門』の解説ポイント
では、小説『羅生門』の凄さとはどういうところにあるのでしょうか。
分かりやすく3つのポイントで解説していきたいと思います。
短い文章で揺れ動く心理描写
小説『羅生門』では6267文字という少ない文字数の中で何度も主人公である男の心理状態が変わっています。
その描写がとても丁寧なので、読者に唐突感を与えないのが凄いポイントだと思います。
「盗人になるのか、ならないのか」この心理描写が本当に卓越しているのです。
序盤の男は
どうにもならない事を、どうにかするためには、手段を選んでいる遑(いとま)はない。選んでいれば、築土(ついじ)の下か、道端の土の上で、餓死(うえじに)をするばかりである。そうして、この門の上へ持って来て、犬のように棄てられてしまうばかりである。選ばないとすれば──下人の考えは、何度も同じ道を低徊(ていかい)した揚句(あげく)に、やっとこの局所へ逢着(ほうちゃく)した。しかしこの「すれば」は、いつまでたっても、結局「すれば」であった。下人は、手段を選ばないという事を肯定しながらも、この「すれば」のかたをつけるために、当然、その後に来る可き「盗人になるよりほかに仕方がない」と云う事を、積極的に肯定するだけの、勇気が出ずにいたのである。
とまぁ、どっちつかずに迷っています。
盗人にならないとなと思いつつ、その勇気が出ないで雨を眺めているのが男でした。
しかし、そんな男が羅生門の上で老婆を見つけるとその心が途端に変化します。
なぜなら老婆が死体から髪の毛を抜いていたからです。
その描写がこちら。
その髪の毛が、一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは、恐怖が少しずつ消えて行った。そうして、それと同時に、この老婆に対するはげしい憎悪が、少しずつ動いて来た。──いや、この老婆に対すると云っては、語弊があるかも知れない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分毎に強さを増して来たのである。この時、誰かがこの下人に、さっきの門の下でこの男が考えていた、餓死(うえじに)をするか盗人になるかと云う問題を、改めて持出したら、恐らく下人は、何の未練もなく、餓死(うえじに)を選んだ事であろう。
この時の下人は悪に対する怒りがあります。
序盤であんなに悩んでいた男はどこに行ってしまったのでしょう。
餓死上等な態度をとっています。
しかしながら、老婆の正義に対する価値観の話を聞いて、再び男の心は動きます。
しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれて来た。それは、さっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうして、またさっきこの門の上へ上って、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然、反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、餓死をするか盗人になるかに、迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心もちから云えば、餓死などと云う事は、ほとんど、考える事さえ出来ないほど、意識の外に追い出されていた。
ほんの少し前まで餓死しても構わないというような心持になっていた男ですが、老婆の話を聞いて一変、餓死など考えることは出来ないという気持ちになっています。
これはつまり、男が盗人になるという決断をしたというシーンになります。
つまり芥川龍之介は6267文字の間で男の気持ちを
盗人か餓死か優柔不断→餓死を選択→盗人を選択
という順番で描いているのです。
悪と正義の道徳心
この『羅生門』という作品は「悪とは何か?正義とは何か?」という芥川龍之介の問いかけがメインテーマになっていると思います。
主人公である男が冒頭では盗人になるか餓死をするのか迷っていたのは、彼の中に盗人(悪)になるのはいけないという道徳心があったからでしょう。
だからこそ、老婆が頭髪を抜いているところを発見した際には凄まじいほどの怒りがありました。
しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くと云う事が、それだけで既にすべからざる悪であった。
これほどまでに正義感にあふれ、悪を嫌っていた男ですが老婆の話を聞くとこの正義感がなくなってしまいます。
なぜならば、老婆には盗人(悪)にならなければならない理由があるからです。
されば、今また、わしのしていた事も悪い事とは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、餓死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。
餓死をしてしまうから盗人(悪)になるという究極の論理を私たち読者に突き付けてくるのです。
これはつまり死か悪かという選択になった時、人間は悪を選ぶという悲しい人間の性の告発でもあります。
実際に第二次世界大戦後、多くの日本国民が闇市に通ったのはそうしなければ生きられなかった時代がありました。
正義を追求したら、餓死をしてしまうという経験を戦後多くの日本人が体験したのです。
この『羅生門』が発表されたのは第二次世界大戦前の1915年ですが、時が経っても国語の教科書に載ったりしているのは間違いなく時代を超えた人間の本質というものをこの小説で表現しているからなのです。
卓越した風景描写
最後は芥川龍之介の文章力に目を向けたいと思います。
羅生門では短い文字数での心理描写もさることながら、芥川龍之介の風景描写も冴えわたっています。
例えば冒頭に
所々丹塗(にぬり)の剥(は)げた、大きな丸柱(まるばしら)に、蟋蟀(きりぎりす)が一匹とまっている。
という荒れ果てた羅生門の描写がます。
その後、
夕冷えのする京都は、もう火桶(ひおけ)が欲しいほどの寒さである。風は門と柱と柱との間を、夕闇と共に遠慮なく、吹きぬける。丹塗(にぬり)の柱にとまっていた蟋蟀(きりぎりす)も、もうどこかへ行ってしまった。
と主人公が現在いる環境の状況描写(温度)に加えて、先ほど登場させたきりぎりすがどこかへ行ったという時間経過の描写もさらりと付け加えています。
わずか6267文字という短さの中に芥川龍之介の才能をギュッと詰め込んだ傑作、それが『羅生門』なのです。
芥川龍之介が描く『羅生門』に興味を持たれた方はどうぞ小説を読んでみて下さい。
Kindle 版だと無料で読むことが出来ますよ!






コメントを投稿